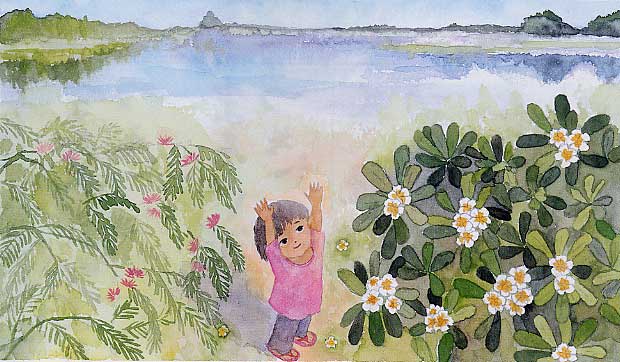 一人のキリスト者のことを紹介しましょう。SVAは仏教系の団体ですが、最初に入会した第一号会員は、なんとカトリック吉祥寺教会の後藤文雄神父(77)なのです。
一人のキリスト者のことを紹介しましょう。SVAは仏教系の団体ですが、最初に入会した第一号会員は、なんとカトリック吉祥寺教会の後藤文雄神父(77)なのです。一九八二年、当時、後藤さんは、身元の引き受け手がいないカンボジア難民を引き受けることになり、子どもたちが母国語を忘れないためにどうしたらいいか悩んでいました。そんな時、SVAが『クメール語(カンボジア語)辞典』を発刊していることを知り、早速、当時、五反田にあった東京事務所を訪ね、その場で会員となったのです。
「SVAはいい仕事をしていると思いました。仏教系の団体であることなど全然気になりませんでした。人間が人間になるお手伝いをするのが我々の仕事です。宗教の違いなど関係ありません」。そんな後藤さんですが、当初は、なぜ自分が里親を押しつけられるのか、憤懣やる方なかったといいます。しかし、「子どもたちの入学式の前の晩でした。川の字になって子どもたちと寝ていたら、体がこわばっているのがわかりました。そして、二人とも小猿のように、私にしっかりしがみついてくるんです。にわか親父がこの子たちの本当の父親になろうと決心したのはこの時でした」。
こうして、後藤さんは九四年三月、最後の子を高校卒業と同時に自立させるまで、つごう十四人の里子を育てあげました。その後、後藤さんがカンボジア支援へ踏み切ったのは九五年のこと。里子の一人、ラーさんがカンボジアの僧侶からの嘆願書を携えて日本に帰ってきたときです。その嘆願書には、村人に希望を与えたい、校舎をつくるのに手を貸してほしい、と切実な思いが綴られていました。その文面が後藤さんを突き動かしたのです。NPO法人も立ち上げ、ラーさんらと共に、カンボジアの辺境の地にこれまで十四の学校を建設しました。昨年、これらの活動が評価され、第十九回毎日国際交流賞を受賞しました。
後藤さんの著書にこんな一節があります。
――イエスは教会の外の貧しい人の中にたたずんでおられる……砦としての教会ではなく、旅する教会にならなければ。宣教の手段としての旅ではない。貧しい人たちとともに生きる道をゆく旅である――。『共に生きる世界』(女子パウロ会)より
上記のイエスを〈文殊菩薩〉に、教会を〈寺〉に置き換えたなら、鎌倉時代の仏僧、叡尊の言葉とさほど変わらないように私には思えます。
叡尊(一二〇一〜一二九〇)は、戒律復興の中心道場として奈良・西大寺を復興させ、ハンセン病者救済、橋・港湾の整備など様々な社会救済事業を行った人です。叡尊は、門弟たちを大和の般若野に集めて次のように語ったといわれます。
――『文殊師利般涅槃経』に生身の文殊菩薩に会おうと思うなら慈悲心を起こせと書かれている。何故ならば、文殊菩薩がこの地上に出現するときは、必ず貧窮孤独の人々の姿となって現れるからである。 さて、この般若野には、差別され、抑圧され、家庭からも社会からも見捨てられた貧窮孤独の人々が肩を寄せ合って生活している。彼らこそ、我々に慈悲の心を起こさせるために地上に現れ給うた文殊菩薩なのだ。
こう語って、叡尊は、竈を作って、入浴と施食を行い、病の介護を行ったといいます。
"イエスは教会の外の貧しい人の中にたたずんでおられる" "貧窮孤独の人々は文殊菩薩の出現である" このように語る二人は、時代の違い、宗教の違いを越えて〈同じ場所〉に立っているとはいえないでしょうか。
〈同事〉の心は、自他一如の心ともいわれます。他の苦しみはわが苦しみ――。人間の悲苦の現実を直視し、大いなる存在とのつながりを見出したとき、人は宗教の違いを越え、支え合い、協力し合えるのかもしれない、と深く考えさせられます。
(了)
(挿絵・長谷川葉月)