『修証義』
曹洞宗総合研究センター特別研究員 丸山劫外
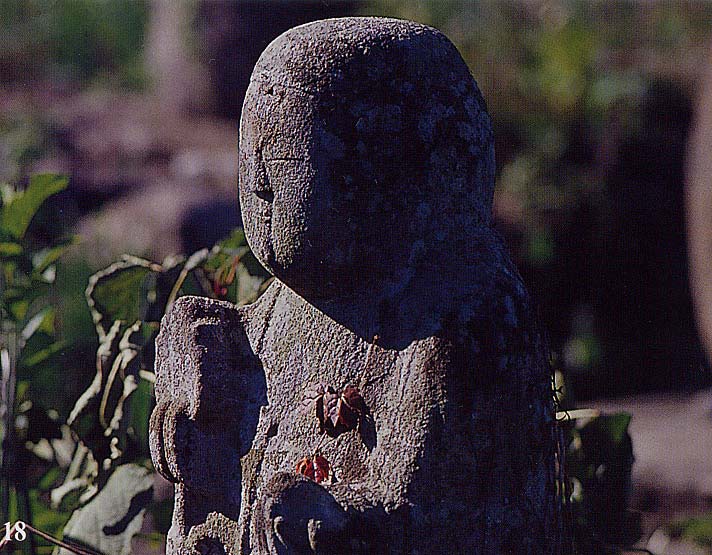
第一章 総 序
(第一節)
生を明らめ死を明らむるは仏家一大事の因縁なり。生死の中に仏あれば生死なし。但生死即ち涅槃と心得て、生死として厭ふべきもなく、涅槃として欣ふべきもなし。是時初めて生死を離るる分あり。唯一大事因縁と究尽すべし。
(訳)生まれるということ、生きているということ、死ぬとはどういうことかをあきらかにすることこそ、仏教者としてもっとも大事なことである。生死の中に仏があれば、迷いはない。ただ生死がとりもなおさず涅槃であると心得て、生死だからといって避けるべきでもないし、涅槃だからといって求めるべきでもない。そうする時、はじめて生死から解脱できるのである。生死をあきらめることこそ、もっとも大事なこととして、深く究めるべきである。
(第二節)
人身 得ること難し。仏法値ふこと希なり。今我等宿善の助くるに依りて、 已に受け難き人身を受けたるのみに非らず、遇ひ難き仏法に値ひ奉れり、 生死の中の善生 、最勝の生なるべし、最勝の善身を徒らにして露命を無常の風に任すること勿れ。
(訳)人間として生まれることはたやすいことではない。仏の教えに出会うのも稀なことである。今、私たちは、過去の善い行いの助けによって、受けがたい人間の身をすでに受けただけではなく、会いがたい仏の教えにも出会っている。生死の中でも、このようなことは善い縁であり、最も勝れた縁というべきではなかろうか。仏法に出会えたという素晴らしい身であるのだから、露のように儚いこの命を、ただ空しく無常の風にまかせてはならない。

解説
『修証義』の一つ一つの文言は、ほとんど道元禅師がお書きになった『正法眼蔵』の中にある文言をつなぎ合わせて、仏教の教えを伝えられるように構成されています。おおうちせいらん大内青巒(一八四五〜一九一八)という方が、原案を作成しまして、それに總持寺のあぜがみばいせん畔上楳仙禅師(一八二五〜一九〇一)と永平寺のたきや滝谷たくしゅう琢宗禅師(一八三六〜一八九七)が修正の筆を加えられて、明治二十三(一八九〇)年に公布されました。
まず、なんといっても仏教徒にとって、最も大事なことは「生死をあきらめる」ことに尽きるとも言ってもよいでしょう。「あきらめる」ということは、降参するという意味ではなく、明らかにするという意味です。
どなたもご自分の命のことを、あらためて考えたとき、不思議と思わない人はいないのではないでしょうか。それでは、この生死をどうあきらめたらよいのでしょう。
道元禅師は『正法眼蔵』「生死」巻で「この生死はすなわち仏の御いのちなり」と言われています。「生死」は流転のすがたですが、ここでは「生と死」「命」として考えてみましょう。
今まで、「私の命は私のもの」「俺の命は俺のもの」と思っていた人が、この命は「仏の御命
であると受けとめたとき、はじめて仏教の信仰がスタートするといってもよいのではないでしょうか。実は正直申し上げますと、私は、ここが自分自身の信仰にとっても、大事なことと、最近ようやく気がついたのです。
私たちは生まれようとして、この世に自ら生まれたでしょうか。また、自ら心臓の動きを止めて命を終えていくでしょうか。そうではなく、不思議としかいいようのないはたらきによって、生まれ、そして死ぬ命ではありませんか。それを「仏の命」と道元禅師は教えて下さったのです。
「仏」とはいいかえれば「真実」と言ってよいでしょうか。「天地」「宇宙」と言ってよいかもしれません。
でも「仏」という表現に、無条件の救いがあるのではないでしょうか。
私の知人に商売に失敗して、借金取りには追われるし、にっちもさっちもいかなくなって、崖の上に立った人がいます。靴を脱いで、合掌したその時、ふと「この生死は仏の御命なり」という言葉が、胸の中に響いたのだそうです。
学生時代にどこかで学んでいたのでしょう。「ほとけのおんいのち」「仏の御命」……。 崖の下で海の波が砕け散る音に、急に足がガタガタとふるえ、「死んではいけない」と思いとどまったのだそうです。彼は、現在では仕事を得まして、きちんと借金を返しながら、生活を立て直しています。なにしろ死ぬ気になったのですから、死ぬ気になればなんでもできる、と分かったそうです。
私も怠け心が起きますと、「この命は仏の御命」と自らに言い聞かせ、励んでいます。
さて、中国の唐の時代に、かっさん夾山ぜんね善会(八〇五〜八八七)という禅僧は、「生死のなかに仏有れば即ち生死に迷わず」と言いました。じょうざん定山しんえい神英(生卒年不詳)は「生死のなかに仏なければ即ち生死なし」と言いました。このようなことを、真剣に論じあいながら、悟りを求めて行脚していたのです。道元禅師はこの二人の言葉をあわせて「生死の中に仏あれば生死なし」とおっしゃったのです。生まれて死ぬ、この絶対的な真実、それが仏の命なのですから、迷いとしての生死はどこにもない、ということです。
この命を大いなるもの(仏といいましょうか)にゆだねつつ、且つ生きている間の舵取りを任されたこの命でもありますから、この命が心の底から喜ぶような生き方をしたいものです。
苦あれば楽あり、楽あれば苦あり、苦は楽であり、楽は苦だともいえます。どちらでもどんとこいといただき、いただき、生きていけば、生死に縛られている思いから解き放たれて、悠々とした日々を送ることができるのではないでしょうか。これが仏教徒としての大事な心構えといえましょう。
またこうして人間として生まれるということ自体なかなか得難いことであり、こうして仏法に出会うということも得難いことだということは、最古の経典といわれている『法句経』第一八二番で説かれています。
私の本師、よご余語すい翠がん巖老師という方は、「けらというものに生まれて泳ぎおり」という俳句を、たびたびお話の中で紹介していました。これは新聞にでも載っていたどなたかの俳句だったようです。
この作者も、けらがけらとして、一生懸命に泳いでいるひたすらな姿に感動したのでしょう。人間も人間として生まれた以上、ひたすらに生きたいものだというメッセージを受け取ります。そして「人間というものに生まれて生きており」と、私は時々思っています。時には自分を励ますように、時には嬉しく、時には悲しい思いの時もありますが、とにかくひたすらにひたむきに人間を生ききりたいと願っています。
人間として生まれた上に、今この世で仏の教えに出会えたことこそ、最も素晴らしいことなのだ、と道元禅師もおっしゃっています。お金儲けや名誉を追いかけて夢中になっているだけでは、この命がもったいない。仏の教えに出会うことこそ、一生をむざむざと空しく過ごさないことといえましょう。
そして、「この生死は仏の御いのち」だと手を合わせつつ生きていけたなら、どんなにか心豊かな一生を送ることができるのではないでしょうか。自分の命を仏の命と拝めたとき、命輝く、と言いたいですね。そして、自分の命だけではなく、自ずと他人の命も拝まずにはいられなくなるでしょう。
勿論、人間だけが仏の命ではなく、けらも猫も犬も牛も熊も猿も草も木も、皆仏の御命ですが、「仏の御命」と「自覚
できるのは人間だけでしょう。もっとも、そのような自覚は、人間だけが必要なのかもしれません。
それぞれの縁によって、仏教だけではなく、キリスト教やイスラム教や、それぞれの宗教との出会いがあるでしょう。それぞれの教えによって、自分の力だけで生きているのではなく、この命、なにか大いなるものに生かされていると自覚して生きられさえすれば、これに勝る幸せはないといえましょう。
先日、友人の妹さんが、突然お亡くなりになりました。電車で出会ったばかりでした。明日はこの身です。いや明日とは言わず、今日かもしれません。露のように儚いお互いの命です。「仏の御命さん、これでよい、今?」と、自分自身に問いかけながら、丁寧に日々を生きていきたいものです。