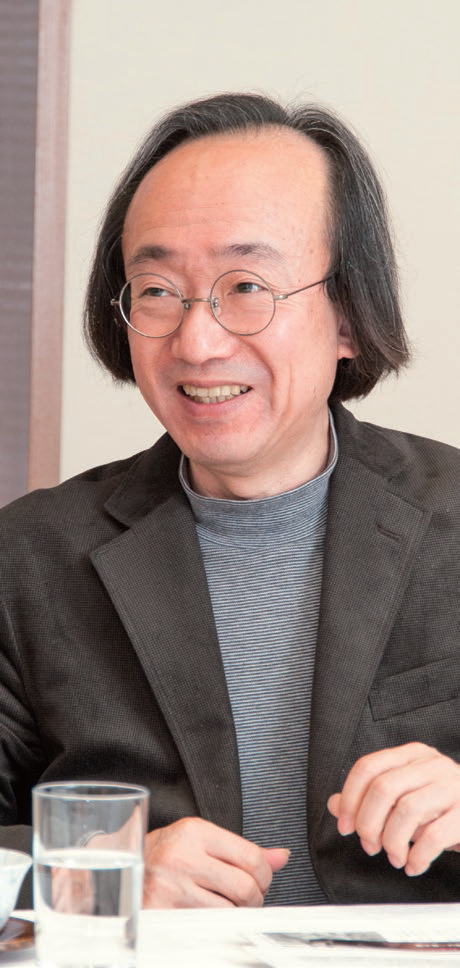 正木 晃(まさき あきら)
正木 晃(まさき あきら)宗教学者。
1953年神奈川県生まれ。
国際日本文化研究センター助教授を経て、慶應義塾大学、立正大学講師。
夏号 特別対談
イスラム世界にどう向き合うか
野中章弘×正木 晃
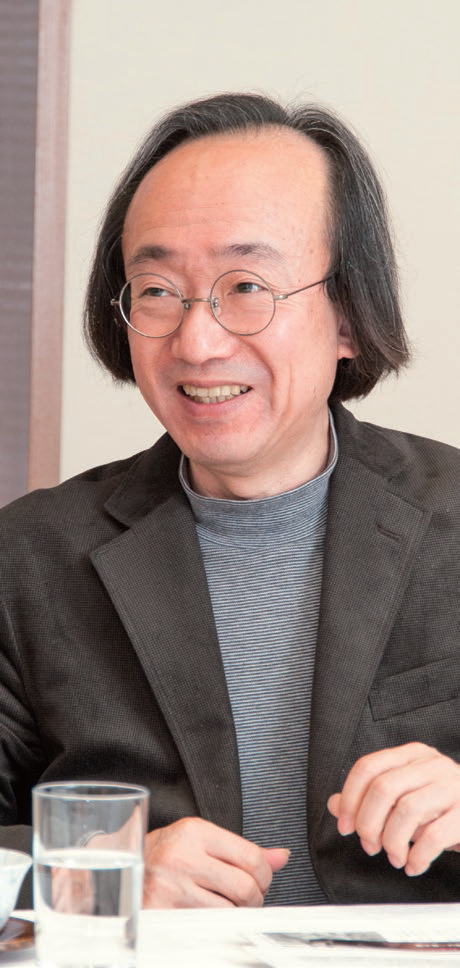 正木 晃(まさき あきら)
正木 晃(まさき あきら)
宗教学者。
1953年神奈川県生まれ。
国際日本文化研究センター助教授を経て、慶應義塾大学、立正大学講師。
 野中章弘(のなか あきひろ)
野中章弘(のなか あきひろ)
早稲田大学大学院教授。
1953年兵庫県生まれ。
フリーのフォトジャーナリストとして活動を始め、現在アジアプレス・インタ―ナショナル代表。
日本人には分かりにくい一神教
野中 今日、僕は正木先生とのお話を、とても楽しみにしておりました。つまり宗教から見たときに、今の世界で起きていることはどう見えるのかというようなことですね。西洋近代というのは、一つ一つ知性を積み重ね、科学で物事を判断していくわけですが、しかしながら、そういう近代というものは行き詰まってきているんじゃないか、そのためいろんなところで破綻が出てきている。イスラムという今のアラブ地域で起きているようなこと、イスラムの世界というのは東南アジアから世界中にまたがるわけですけど、そういう中でイスラム国の邦人人質殺害事件が起きて、日本人にとっては非常にショックなわけです。これをどう読み解いていったらいいのか。
テレビや新聞はみんな勝手なことを言って、なかなか核心に迫るような話がない。むしろ非常にステレオタイプ的な、イスラム=テロリストという図式化がどんどん進むんじゃないかと思うんです。その辺からまず。
正木 まず宗教という言葉からイメージされるものが、日本人が考える宗教と一神教、特にイスラム教徒の考える宗教とは違うだろうと思います。私たちは宗教という言葉で全部一緒くたにしてしまって、宗教だから人を殺さないとか、宗教だから平和を求めるのは当たり前だというけれど、そのときに日本人が考えているのは仏教や神道、あるいはそのベースにあるアニミズム的な世界観からの宗教だと思うんです。
ところが、一神教における宗教というのは、逆に言えば一神教の人たちからすれば、日本人の考える宗教は宗教ではない。習俗であったり、もっとほんわかしたものだと思うんですね。例えば、戒律の戒という字があります、サンスクリットでシーラと言いますが、これは本来、自発的な誓いという意味なんです。いろんな問題が起こったときに、ブッダを中心にみんなで会議をして、こういうことが起こらないようにするにはどうしたらいいだろうか、ということで決めた規定みたいなものが戒だと言われています。
同じ戒でも、旧約聖書に出てくるモーセの十戒というのは、人間の知性や理性では解決できない問題に対して、全知全能の神が、こうやればちゃんと生活できるんだよという形で決めてくれたもの。日本語にすると掟で、ある意味で強制されるものですね。神が掟を授け、それを守っていくことが宗教生活である。ここから何が出てくるかというと、原則として一神教では修行をしてはいけないわけです。つまり、修行をすると神の手を外れることになるし、自発的な行為になるので、それは基本的にはしてはいけない。
 「ミーラージュ・ナーメ」の彩色写本より「天国」(トルコ東部、15世紀)
「ミーラージュ・ナーメ」の彩色写本より「天国」(トルコ東部、15世紀)
一方、仏教の場合、まず自らが修行をしなければ何にも始まらないわけです。そこの一点を取っても恐らく仏教がイメージしている宗教と、イスラム教が考えているような宗教はずれがあって、このずれというのは、私たちが考えているよりずっと大きいのではないかと思うんです。まずその辺のことが一般の日本人には理解できてない。同じ宗教だという枠組みで論じようとしたりすると、あまりにも枠組みが大きすぎて、論じる対象としてはあいまい過ぎるなというのが、私の基本的な印象なんです。
 「ムハンマドの昇天」ニザーミー作叙事詩「ハムセ」に付されたミニアチュール(北インド、16世紀)
「ムハンマドの昇天」ニザーミー作叙事詩「ハムセ」に付されたミニアチュール(北インド、16世紀)
日常生活における宗教の重み
野中 日本人の考えているイスラム観と、イスラムそのものの在り方との間の大きなギャップということ、僕はちょっと違った面からお話したい。つまりそれはギャップというより、われわれがイスラムを理解してないという意味でのギャップなんですね。それはしかし、現実的にわれわれの身の回りにイスラム教徒があまりいないということが大きいでしょう。しかもイスラム教というのは一神教であり、もともと遊牧の民の宗教であり、気候風土も日本と真逆のような所で生まれ、日本人と全く違うメンタリティーの中で育ってきたものです。
そういうことに対して、われわれがイスラムを理解しようとするときに与えられている材料というのは、非常に断片的な知識ですよね。豚肉を食べてはいけないとか、妻は四人まで持てるとか、恐らくほとんどの人はコーランを読んだこともないでしょう。僕はアジアプレス・インターナショナルというジャーナリストたちのネットワークをやっているんですが、そこにパキスタン人のメンバーがいて、彼は高等教育を受けたエリートですけれども、一時間ぐらいコーランを暗記して言うことができる。だけど僕の周りの日本人で、お経を一分以上読める人間、はて、どれだけいるか、ほとんど皆無です。
つまり、イスラムの地域に住む人たちにとっての宗教の重みと、われわれの日常生活の中における宗教の重み、比重といいますか、それはもう随分と違うということなんです。もう一つ、やはりジャーナリズムの世界の問題でもあるんですけれども、さまざまな形で今、テロの脅威にさらされているといったときに、テロの主体はほとんどがイスラムであるということですね。二〇〇一年の九・一一、あの世界同時多発テロが起きたとき、当時のブッシュ米大統領は十字軍という言葉を使ったり、それからイスラムは遅れた宗教であり、中世的な宗教であり、野蛮な宗教である。そういう発言がなされたわけです。
そういう考えが浸透した上で、アフガニスタン侵攻とか、イラク戦争が始まった。つまり、欧米の世界のほうが上等な文明と宗教観と社会を持っている、イスラムは遅れていると、そういう差別意識を流布した上で、そうすると戦争しやすいんですよ。例えば僕がイラク戦争を取材して、そこでアメリカ兵たちに聞く、何のために君たちはイラクへ来たのか。すると、これは独裁者からイラクの人々を解放するためだ、民主主義をもたらすための戦争だと言うわけです。
それは自分たちの優れた民主主義を持ってきてやって、アメリカ兵だってもう四千数百人、イラクで死んでいるわけです。これだけの血を流して、おまえたちの最大の独裁者を排除してやっているのに、何でおまえたちはありがたくそれを受け取らないのかという、イラクでもそうですしアフガンでも同様なんですね。結局、そういう欧米の側が正義であり、優れているという価値観に対して、アラブ、イスラムの人たちの多くが反発を感じている。ところが、そういうことが欧米の側に全く意識されてないんですよ。
イスラム対キリスト教、対立の由来
野中 ですから、イスラムの人たちがなぜああいうことをするのか、なぜああいう形で反発があるのか、まずそれを学ぶべきです。彼らがどういう主張をして、どういう人生観をもって生きているのかということを学んだ上で、そこから話をしていかなければいけないと思うんです。今イスラムで起きていること、そしてイスラム教とはどういう宗教なのかということをきちんと学ぶ。そういう姿勢を取らなければ、いつまでたっても歩み寄りというか、相互理解は進まない。イスラム教は何かちょっとおかしな宗教だね、あそこからテロリストも出てくるしという、そういう図式化されたイメージが壊せないと思う。
正木 私の立場からすると、少し歴史をさかのぼって地中海の東のほう、いわゆるパレスチナを中心にするような地域で、長らくキリスト教の勢力とイスラム教が戦い続けてきた歴史があります。七世紀の初頭あたりからイスラムがどんどん出てきて、十世紀ぐらいまではイスラムが恐らく、軍事的にも経済的にも、それから社会システムの上でも一番優れていたでしょうね。その後、十字軍が起こる。はっきり言って十字軍というのはヨーロッパの遅れた首長どもが略奪に行ったという話があるぐらいで、かなりひどいものだった。とにかく中世の歴史をたどっていきますと、血で血を洗う抗争です。
さらにその後、今度はモンゴルが入ってきて、ぐちゃぐちゃな状態になってくる。モンゴルと戦うためにイスラム教徒の一部とキリスト教徒が手を結ぶとか、あるいは今度はモンゴルとイスラム、モンゴルとキリスト教という具合で、滅茶苦茶な状態になってしまうんです。そういう抗争の歴史がずっと続いていて、ヨーロッパあるいはそこから分かれて出たアメリカ人の心の中に、常にイスラムは敵対者という思いが抜きがたくあると思うんです。キリスト教とイスラム教の対抗関係、対立関係というのはものすごい歴史の厚みがあって、今始まった話ではないということです。
野中 まさにそのとおりですよね。
正木 今申し上げたように、十世紀、十一世紀ぐらいまではイスラムのほうが圧倒的に優位だった。コーランを読んでもそうなんですけれども、宗教というのは、よい宗教、悪い宗教なんていう話とは別に、常に自分が最高位にあるわけです。相手は全部下なんです。そのせめぎ合い、ぶつかり合いというのがずっと今日に至るまであって、中世のキリスト教世界は神学のレベルでも、イスラムの影響を非常に強く受けてしまっていますし、イスラム優位だったことは間違いない。
特に中世ヨーロッパで知識人の知識人たるゆえんは、アラビア語ができることだった。というのはご存じのとおり、アリストテレスの哲学は一度、全部アラビア語に翻訳をされて、北アフリカからジブラルタル経由、イベリア半島を通じてパリへ入るわけです。それぐらいアラビアというか、イスラム文化のほうが優位だったわけです。それが近世の末期あたりから逆転して、今までやられる側だったキリスト教が今度は優位になった。そういう歴史があって、実はこの関係はそう簡単には互いに克服しがたいんだろうなという気がするんです。
 『日亜対訳・注解 聖クルアーン』より
『日亜対訳・注解 聖クルアーン』より
イスラムの問題はイスラム内部で解決するしかない
正木 日本人の多くはそういう歴史的な厚みをほとんど知らない、だってイスラムを知りませんでしたからね。戦前は大川周明あたりから始まるわけですが、それもご存じのように、大東亜共栄圏をつくるためにイスラム教徒と手を組もうという話になって、代々木上原にあるモスクはそのためにつくった。ですから戦前における日本では、イスラムに対する評価は高いんですね、知識人の間では。ムハンマドというのは大変な英雄だという言い方をしています。
野中 それは面白いですね。
正木 ところが、戦後になると大東亜共栄圏自体、全面否定されます。そういったものがみんな隠されてしまった。
野中 正木先生が言ったまさにそのとおりで、日本人の今、知性的な面での弱点というのは、物事を歴史的な文脈で理解するという姿勢が非常に弱いんですね。われわれジャーナリストからすると、今起きていることは社会現象ですから、必ず原因があるわけです。それはさかのぼっていかなきゃいけない、つまり歴史を学ぶということです。どこまでさかのぼるか、少なくとも数十年、数百年という形でさかのぼって、今これがあるという、そういう歴史の流れの中で見なきゃいけないのに、今の新聞とかテレビは現在しか見てない。僕から見ると、非常に短絡的で単なるリアクションなんです。
だから、歴史的な文脈で見るということになれば、例えば今問題になっているイスラム国も、これも彼らが五年、十年、二十年、どういうふうな世界をつくろうとしているかというと、第一次世界大戦後にヨーロッパが定めた国境線を全部廃止しようと。彼らのビジョンというのは、西はスペインからアフリカの地域、そして中東、中国あたりまでを覆う大帝国です。この発想というのは、多くのアジアの地域、あるいはアフリカの地域がヨーロッパの植民地になり、勝手に国境線を決められて分断されてしまった。そういう植民地主義に対しての抵抗というようなものが明らかにあるんですね。
正木 イスラムという言葉でひとくくりにできないものがありすぎます。それは仏教だってそうで、チベット仏教とスリランカの仏教と日本の仏教、一緒にはならないです。でも欧米人からすると、全部まとめてブッディズムだという。それと同じようなことを、われわれもイスラムに対して行っている可能性が多々あると思うんです。相当ソフトなイスラムからハードなイスラムまでさまざまあって、一番極端な例はイスラム国だろうと思いますけれども、だからといって、あれをもって全部イスラムを代表させるということは、これまた不可能です。今すぐに結論めいたことは出てこないんですが、イスラムの問題はイスラム内部で解決するしかないんです、本来的には。
野中 それが基本ですね。