『宝慶記』の謎を探る
――〝宝慶〟とは何か
歴史ルポライター 深見六彦
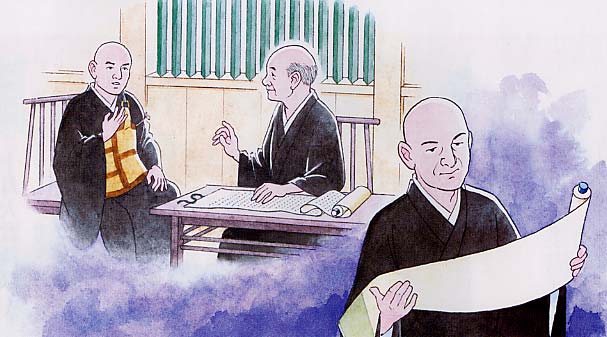
道元さまの思い出(14)
『宝慶記』の謎を探る
――〝宝慶〟とは何か
歴史ルポライター 深見六彦
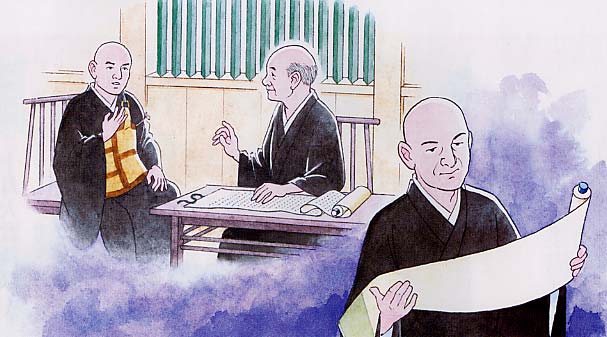
中国から来日した寂円(じゃくえん)は日本語が話せたのだろうか。筆者は充分通じたと考えている。この時、日本に来てからすでに三十年以上経っているうえ、まわりはほとんど日本人である。たとえほとんどの時間を修行に費やしていたとはいえ、もしかすると来日数年で日本の言葉にも慣れ堪能になっていたと思える。今風に言えば京訛り、福井訛りだったろうが……。もちろん書の腕前もなかなかのものであったに違いない。
道元禅師が亡くなられて七年、永平寺を降り現在の福井県大野市の奥深い山中において坐禅行を始めた寂円の周辺も次第に賑やかになっていった。遠くから見つめるだけだった周辺の村人たちも収穫した野菜等を持ち寄るようになってきたし、二人の若者犬吉と牛兵衛の献身的な働きで形ばかりとはいえ草堂が出来ると、噂を耳にした若き修行僧が訪れることも多くなってきた。さらには伊自良知俊(いじらともとし)の力で立派な堂宇が建ち並ぶ頃には、寂円と宝慶寺(ほうきょうじ)の名声は越(こし)の国中に広まっていた。
ところで寂円開山の宝慶寺の「宝慶」とは何か、読者のみなさんはご存知だろうか。実は宝慶とは中国宋(そう)の時代の年号のひとつである。道元禅師が明全和尚(みょうぜんおしょう)と共に宋国に渡ったのは一二二三年のこと。禅師が天童山景徳禅寺での修行の後、阿育王山広利寺や大梅山護聖寺といった諸山求法の旅を終えて再び天童山に戻ったのが一二二五年、宝慶元年春であった。この時、その後の寂円の人生を決定づける道元禅師との遭遇があった。出会いの様子は本誌七十三号の「道元さまの思い出――第二回」で書いたのでここでは省く。ともかく寂円が道元禅師と師弟の契りを結んだのも、先師如浄禅師が遷化されたのも宝慶年間だったので、この年号は寂円にとって生涯忘れることの出来ないものになったのである。寂円が寺の名を宝慶寺としたのも頷けよう。
さて、愛知県豊橋市東郷町にある仙壽山全久院(ぜんきゅういん)には、永平寺二世懐奘禅師御真筆の『宝慶記』が保管されている。『宝慶記』とは何か。「宝慶」とあるからには寂円と関係があるのだろうか。しばらくこの話を進める。
寂円でございます。
方丈にて懐奘さまより賜った『宝慶記』一巻を久し振りに手にしております。これは道元さまが宋にて先師如浄さまの元でご修行中、宝慶元年夏ころから翌年の暮れ近くまでのお二人の問答を、道元さまご自身が書き記したものが元になっているのです。道元さまはよく如浄さまのお部屋をお訪ねになり、求法のための質問をされました。また如浄禅師はしばしば道元さまをお部屋にお招きになっては、作法など細かなことまでご指導されておりました。この時のお二人のご様子はなつかしい思い出です。
寂円が語るように『宝慶記』の元になったのは、景徳禅寺で道元禅師が如浄禅師に質問し指導を受けたあれこれを、問答の形そのままにメモしたものである。当時、寂円は如浄禅師の近くで侍僧としてお勤めをしていたので、このあたりのことは良く知っていたと思える。それでは何故、禅師がメモをしてから五十年近くも経っているというのに、一巻にまとめられた『宝慶記』を寂円は所持しているのであろうか。しかも懐奘禅師から貰ったものらしい。
そこで、その謎を解明すると同時に、『宝慶記』にはいったいどんなことが書かれているのかなどを、語りたいと思う。
(以下次号)